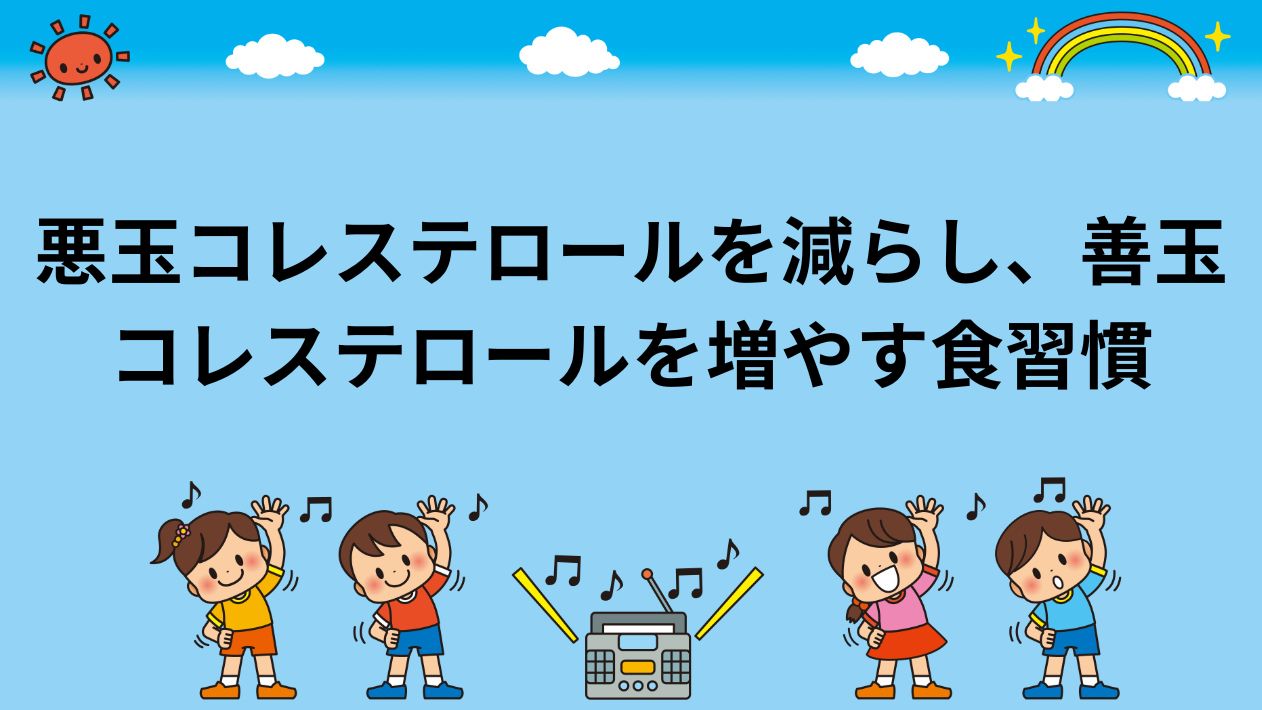健康診断の結果表に並ぶ、カタカナやアルファベットの項目。その中でも「コレステロール」という言葉に、一喜一憂している方は少なくないでしょう。特に「悪玉」と「善玉」という言葉が、私たちの不安を煽ることもあります。しかし、コレステロールは本来、私たちの体にとって必要不可欠なものです。問題となるのは、その「種類」と「バランス」です。増えすぎると健康リスクを高める悪玉コレステロールと、それを回収してくれる善玉コレステロール。この二つのバランスが崩れる原因の多くは、日々の食習慣に隠されています。ですが、裏を返せば、食習慣を見直すことで、このバランスは改善できる可能性が高いということです。この記事では、難しく考えがちなコレステロール対策を、毎日の「食」という身近な視点から解きほぐし、今日から実践できる具体的な習慣を、分かりやすくご紹介していきます。
なぜバランスが大切? 悪玉と善玉の役割
コレステロールと聞くと、漠然と「健康に良くないもの」という印象を持つかもしれませんが、実は私たちの体を作る細胞の膜や、ホルモンの材料となる重要な成分です。大切なのは、その働き手である二種類のコレステロール、通称「悪玉」と「善玉」の働きを理解し、両者が協力し合える環境を整えることです。ここでは、なぜ一方が悪玉と呼ばれ、もう一方が善玉と呼ばれるのか、その理由と、両者のバランスが崩れると何が問題なのか、そしてコレステロールと密接に関わるもう一つの脂質についても解説します。
悪玉コレステロール(LDL)とは何か
悪玉コレステロールは、正しくはLDLコレステロールと呼ばれます。この「悪玉」という不名誉なあだ名は、その性質に由来します。悪玉コレステロールの主な仕事は、肝臓で作られたコレステロールを、全身の細胞に届ける「配達員」のような役割です。この役割自体は、体にとって必要不可欠なものです。しかし、問題は「増えすぎた」場合に起こります。食生活の乱れや運動不足などで悪玉コレステロールの量が必要以上に増えてしまうと、配達しきれなかったコレステロールが血管の壁に少しずつ溜まっていってしまいます。これが積み重なると、血管の通り道が狭くなったり、硬くなったりする原因となり、健康な血液の流れを妨げるリスクを高めてしまうのです。だからといって、悪玉コレステロールがゼロであれば良いというわけではなく、あくまで「適正な量」を保つことが重要なのです。
善玉コレステロール(HDL)の働き
一方、善玉コレステロールは、正しくはHDLコレステロールと呼ばれます。こちらは「善玉」という名前の通り、私たちの健康維持にとって非常に頼もしい存在です。善玉コレステロールの主な働きは、悪玉コレステロールとは逆の働きをします。つまり、血管の壁に溜まった余分なコレステロールや、使い古されたコレステロールを回収し、肝臓に運び戻す「お掃除役」あるいは「回収員」のような役割を担っているのです。肝臓に運ばれたコレステロールは、再利用されたり、体外へ排出されたりします。善玉コレステロールが十分に働いていれば、悪玉コレステロールが増えすぎても、血管の健康が保たれやすくなります。しかし、善玉コレステロールが少ないと、この「お掃除」機能が低下し、悪玉コレステロールが溜まりやすい状態になってしまうのです。
コレステロールと中性脂肪の関係
コレステロール値のバランスを考える上で、切っても切り離せない存在が「中性脂肪」です。中性脂肪は、私たちが活動するためのエネルギー源として体内に蓄えられる脂質の一種です。食事で摂ったエネルギーのうち、使い切れなかった分が中性脂肪として蓄えられます。この中性脂肪が増えすぎると、それ自体が健康リスクとなるだけでなく、コレステロールのバランスにも悪影響を及ぼします。具体的には、中性脂肪が増加すると、善玉コレステロールが減少し、悪玉コレステロールが小型化して、より血管の壁に入り込みやすい「超悪玉」とも呼べる状態に変化しやすくなることが知られています。中性脂肪は、特にアルコールの飲み過ぎや、甘いもの、炭水化物の摂り過ぎで増えやすいため、コレステロール対策は中性脂肪対策とセットで考える必要があるのです。
悪玉を増やす「控えるべき」食習慣
まず、悪玉コレステロールを増やす最大の要因は、肉の脂身やバター、生クリームなどに多く含まれる飽和脂肪酸であること、これらは体内でコレステロールの合成を促進するため、霜降り肉や洋菓子などでの過剰摂取に注意し、その頻度や量を見直すことが改善への第一歩となります。
次に、卵やレバー、魚卵といったコレステロールを多く含む食品について、かつては厳しく制限されていましたが、近年の研究では、食品からの摂取量よりも飽和脂肪酸の影響の方が大きいという「誤解と真実」、とはいえ、飽和脂肪酸も含む食品があるため、無制限ではなく適量を守って楽しむことです。
善玉を増やし悪玉を抑える食材選び
まず、悪玉コレステロールを上げにくい不飽和脂肪酸を「良い脂質」として取り入れることを推奨しました。オリーブオイルやキャノーラ油に含まれる一価不飽和脂肪酸や、青魚などに含まれる多価不飽和脂肪酸は、調理に使う油を悪い油から置き換える意識で活用することが大切です。
次に、青魚(サバ、イワシなど)の油に多く含まれるEPA・DHA(オメガ3系不飽和脂肪酸)の強力な効果について説明しました。これらは中性脂肪を減らし、血液をサラサラにすることで、コレステロールバランスを改善し、健康維持に貢献するため、週に数回の摂取をすすめます。
大豆製品(豆腐、納豆など)に含まれる良質な植物性たんぱく質やイソフラボンが、悪玉コレステロールを下げる働きを持つことを解説しました。肉料理の一部を大豆製品に置き換えるといいでしょう。
食材を活かす「食べ方」と「調理法」
まず、食物繊維がコレステロールの吸収を抑える「お掃除役」として重要です。食物繊維が豊富な野菜や海藻類から食べ始める「食べ順」を実践することで、糖質や脂質の吸収を穏やかにする効果が期待できます。
次に、食物繊維摂取の目標である「野菜 350g」を達成する。生野菜だけでなく、加熱して「かさ」を減らす(お浸し、スープなど)ことや、毎食小鉢一皿分を意識することで、無理なく多くの野菜を摂取する習慣を意識しましょう。
油の摂取を減らすための賢い「調理法」で、「揚げる」「炒める」といった油を多く使う方法から、「蒸す」「茹でる」「煮る」「焼く(網焼き)」といった方法にシフトチェンジすることもおすすめです。。テフロン加工のフライパンや電子レンジの活用など、具体的なテクニックが、摂取する脂質(飽和脂肪酸)を減らす上で非常に効果的です。
食習慣と生活全体で考えるコレステロール対策
悪玉コレステロールが血管を傷つけるのは「酸化」された時で、この酸化を防ぐ力である「抗酸化作用」を持つ食品(ビタミンC・E、ポリフェノールなど)をしっかり摂ること。
食事とセットで行うべき対策として、「運動と禁煙」です。ウォーキングなどの有酸素運動は中性脂肪を減らし、善玉コレステロールを増やす効果がある一方、喫煙は善玉コレステロールを減らし、悪玉コレステロールを酸化させるため、禁煙を強く勧めます。
アルコールとの付き合い方は、適量ならば良いとされる説もありますが、飲み過ぎると中性脂肪が急増し、結果的にコレステロールバランスを悪化させてしまうため、休肝日を設けるなど、摂取量の厳格な管理が不可欠です。
まとめ
健康診断でコレステロールの値に注意が必要とされた時、私たちはつい不安になりがちです。しかし、悪玉コレステロールと善玉コレステロールのバランスは、日々の食習慣の積み重ねによって大きく左右されるものであり、それは同時に、私たちの意識と行動によって改善できるものでもあります。大切なのは、悪玉コレステロールを増やす飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の多い食品を「控える」意識と、善玉コレステロールの維持や悪玉コレステロールの排出を助ける食物繊維、青魚(不飽和脂肪酸)、大豆製品などを「積極的に摂る」意識を、両輪で持つことです。さらに、油を控える調理法を選び、野菜から食べる順番を意識し、抗酸化作用のある食品を摂り入れること。そして、食事だけでなく、適度な運動や禁煙、節度ある飲酒といった生活習慣全体を見直すことが、コレステロールのバランスを整えるための確かな道筋となります。完璧を目指すあまり窮屈になるのではなく、まずは一つでも二つでも、できることから始めてみませんか。